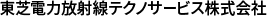放射線を知る
GM管式検出器
ガイガー=ミュラー計数管式検出器 なぜ長年にわたり利用されるのか?
〇歴史
1895年 ヴィルヘルム・レントゲンによってエックス線が発見されてから放射線と放射性物質の研究が始まり、それと同時に放射線検出器・測定器の研究と開発が始まりました。これまでに各種の放射線検出器・測定器が考案され、その改良が続いていますが、単にGM管と呼ばれることも多いガイガー・ミュラー計数管式検出器(以下、GM管式検出器)は1920年代に開発された放射線検出器*1とされ、最も古くから利用されている放射線検出器の一つです。その名称は開発と改良に携わったハンス・ガイガーとヴァルター・ミュラーに由来しています。
*1 GLENN F.KNOLL著 酒井英次・木村逸郎 訳.放射線計測ハンドブック(第4版).
日刊工業新聞社.2013.211p
〇日本国内での利用について
日本国内においては、①主にバックグラウンドレベルを測定するモニタリングポストでは精度が高く安定した測定が可能なNaI(Tl)シンチレーション式検出器を利用した機器が、②個人線量計など小型の線量(率)測定機器については光電子増倍管を使わないために小型かつ軽量、測定精度の高いCsI(Tl)シンチレーション式検出器を利用した機器が、③汚染サーベイメータなどベータ線測定機器については検出面を拡大しやすいプラスチックシンチレーション式検出器が、それぞれGM管式検出器に代わる検出器として浸透しています。
〇海外での利用について
以上のように日本国内では影が薄くなりつつあるGM管式検出器ですが、海外では国内ほど代替が進んでいないようです。世界各国の動向を正確に把握することは困難ですが、原子力規制委員会が行った調査結果*2によると、特に欧州のモニタリングポスト(プルーム通過監視)はGM管式検出器を利用した線量計が中心であり、日本国内で一般的なNaI(Tl)シンチレーション式検出器を利用した線量計は殆ど配備されていないようです。また、同報告には英国放射線防護庁NRPB発行のハンドブックについても記述があり、その中では対象核種によりますが線量率、線量、汚染の何れの測定についても推奨計測器としてGM管式検出器が記載されています。なお、欧州においてはNaI(Tl)シンチレーション式検出器については、線量(率)測定用ではなく、主に現場でスペクトル測定を行うことにより汚染の状況を把握するための利用が想定されているようです。
*2 原子力規制委員会/公益財団法人原子力安全技術センター
平成26年度原子力施設等防災対策等委託費(環境放射線モニタリング国際動向調査)
事業 報告書 72-75p ,187-195p
海外の動向については、日本アイソトープ協会のウェブサイト内、放射線設備機器ガイド*3に掲載されている計測機器(個人線量計やサーベイメータ)におけるGM管式検出器の割合も参考になります。代理店により多数の計測機器(個人線量計やサーベイメータ)が輸入されていますが、GM管式検出器を利用した測定機器が多数供給されており、現在も放射線測定分野で広く使用される検出器の一つと言って良いと考えられます。
*3 公益社団法人 日本アイソトープ協会 放射線設備機器ガイド Gradin
〇GM管式検出器を採用する利点
特に海外においてGM管式検出器が一定のシェアを確保している理由の一つには導入・運用コスト面の優位性が考えられます。
具体的には、検出器の製造という点では、①窓材料を変えることでアルファ線、ベータ線、ガンマ線用の検出器が製造可能である。②機械的・電気的な構造が単純であり生産性を高めることが比較的容易である。③同じ構造で大きさを変えることにより測定範囲のことなる検出器を製造できる。などが挙げられます。
また、測定器の製造という点では、①ガンマ線用の検出器としては機械的に堅牢な検出器で個人線量計など落下に対応し易い。②工場において調整を要する工程が少ない。③検出器プローブを変えることで各種測定器を揃えることができる。などが挙げられます。メーカーにとっては類似の設計により数量を確保することができることから価格面での優位性を発揮できると考えます。
表 検出器の種類と対応する放射線の種類
| GM管式 | 電離箱式 | NaI/CsI シンチレーション式 |
プラスチック シンチレーション式 |
|
|---|---|---|---|---|
| アルファ線 | △ | × | × | ○ |
| ベータ線 | ○(端窓型) | △ | × | ○(薄型) |
| ガンマ線 | ○(窓無型) | ○ | ○ | △(大型) |
さらに、運用面から考えた場合、GM管式検出器は温度機構が不要になる点もコスト面に影響を与えます。温度依存性は認められるものの単純に検出器出力パルスを計数すれば良いGM管式検出器は、検出器出力パルスの波高電圧の変動が測定結果に影響を与えるNaI(Tl)シンチレーション式検出器と比較して、原理的に温度影響を受けにくいと言えます。また、NaI(Tl)シンチレーション式の場合、特に低温から高温へ急激な温度が変化した際に、結晶中心部と外縁部の膨張の差により亀裂を生じる可能性があり、屋外に配備されるモニタリングポストなどにおいては温度制御を行うことが一般的です。
〇今後について
近年、海外製測定機器においても数10μSv/h程度までの低線量率領域についてはCsI(Tl)シンチレーション式検出器が勢いを増しているようです。しかし、この場合でもGM管式検出器を組合わせることで高線量率領域をカバーしているケースが多く、今後もGM管式検出器は利用されていくものと考えられます。